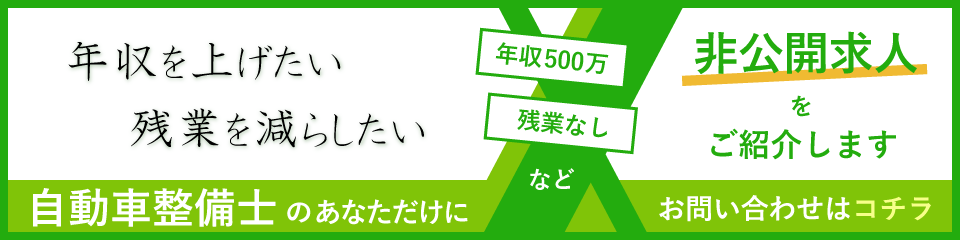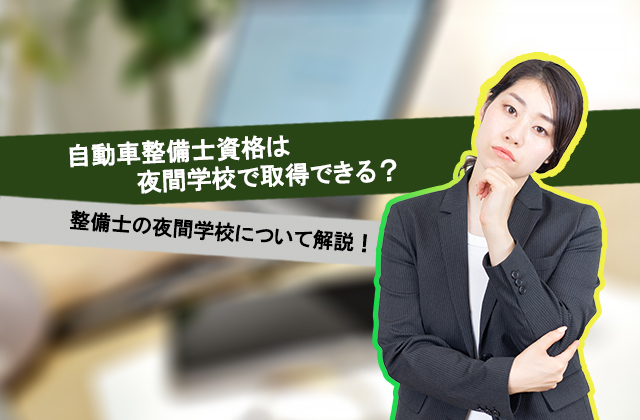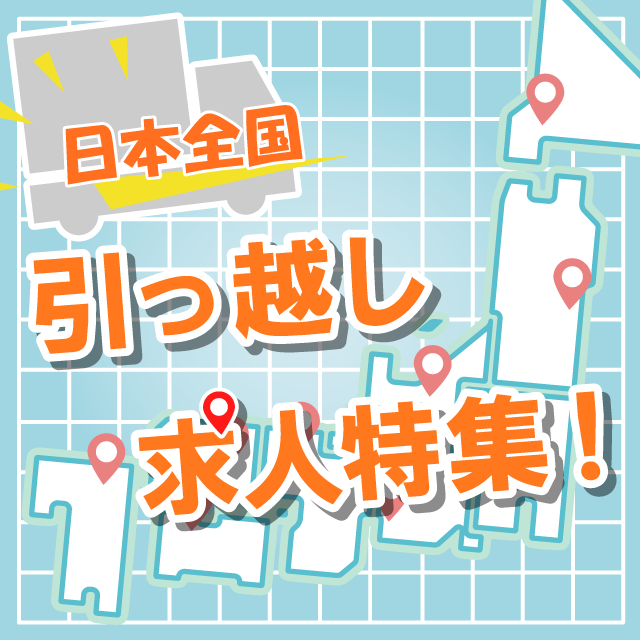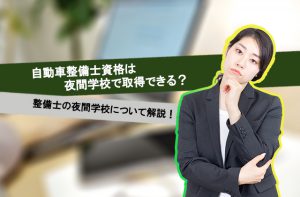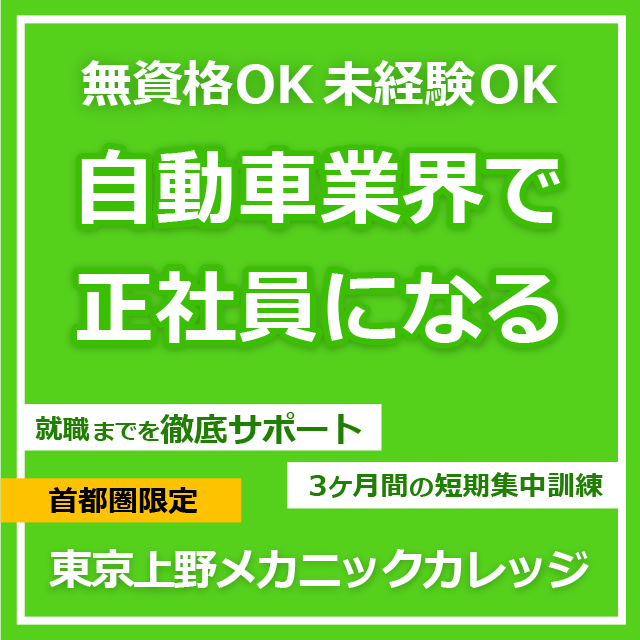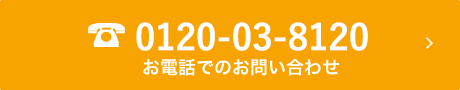自働車整備工場には認証工場と指定工場の二種類があります。名前がなんとなく似ている認証工場と指定工場ですが、どのような違いがあるのでしょうか?この記事では、認証工場と指定工場の違いについて解説致します。
【認証工場】について

「認証工場」でできる業務
国から自動車の安全に大きく関わる整備や調整作業、つまり「分解整備」を行っても良いという許可を得た工場のことを認証工場といいます。
現在、整備工場が取得できる認証は3パターンあります。
①分解整備のみ
②電子制御装置整備のみ
③分解整備と電子制御装置整備
①⇒分解整備の認証工場では、自動車の原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・連結装置を分解し、修理することが可能です。まさに皆さんが想像する「整備」ができるようになるのです。
②⇒電子制御装置整備のみの認証工場では、自動ブレーキなどのためのカメラやレーダーのエーミング作業や、センサー類が取り付けられた窓ガラス・バンパーの取り外しなどを行うことが可能です。
③⇒両方の認証を受けた工場では、すべての整備・修理・調整を行うことができます。
認証を取っていない工場でこれらの整備を行うと、違法整備となり、法に課されてしまいます。
「認証工場」の認証を受けるための条件
従業員について
認証工場は、整備主任者を1人以上、分解整備に従事する従業員を2人以上置くことが求められます。また、従業員のうち2級または1級の整備士が1人以上、かつ3級以上の整備士が行員数の1/4以上の人数が必須です。
作業場について
車両整備のための作業場にも規定があります。乗用の普通自動車を取り扱いの場合、最低でも車両整備場は4m×8m、部品整備場は8㎥、点検作業場は4m×8m、車両置き場は3m×5.5mが必須となります。大型車等を扱う際は規定が異なりますのでご注意ください。
設備や備品について
原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・連結装置のうち、どの装置を整備対象にするかにより必要な設備は異なります。
エア・コンプレッサやトルクレンチ、サーキットテスタなどは、どの装置が対象であっても必須です。
【指定工場】について

「指定工場」でできる業務
認証工場のうち、さらに指定工場としての要項を満たす工場のことを指定工場と呼びます。
指定工場は「民間車検場」とも呼ばれており、その名の通り工場内に車検の検査ラインを保有しています。認証工場では工場内で車検を行えませんが、指定工場では車検前後の整備から車検まですべての整備を工場内で行うことが可能です。
「指定工場」の認証を受けるための条件
従業員について
指定工場は従業員を5人以上雇用しなければなりません、そのうち、車検後の車がきちんと保安基準を満たしているかのチェックを行う自動車検査員を、1人以上置くことが義務付けられています。
また、従業員のうち整備士の人数が行員数の1/3以上である必要があります。
作業場について
乗用の普通自動車を取り扱いの場合、認証工場に必要な屋内作業場のほか、64㎡以上の現車作業場と完成検査場が必要となります。現車作業場については、車両整備場などの屋内作業場と兼用が可能です。
設備や備品について
自動車分解整備事業に必要な設備に加え、サイドスリップテスタなどの車検に必要な設備が必須となります。
指定工場と認証工場の違い
前の章では指定工場と認証工場の要項について詳しく説明しました。
2つの大きな違いはやはり、指定工場では工場内で車検ができて、認証工場では工場内で車検ができないことでしょう。認証工場でも車検の依頼を受けている工場はありますが、工場内に車検ラインがないため、陸運局に持ち込んで最終検査を行う必要があります。
自分が車を預ける整備工場がどちらになるのか、一度調べてみるのもいいかもしれませんね。
最後に
認証工場と指定工場の違いについてご紹介しました。この記事を読まれた方は、自動車整備士の転職はエージェントがおすすめ!も一読することをおすすめします。
最後になりましたが、弊社ダイバージェンスでは自動車業界で働きたい「自動車整備士」「自動車検査員」向けの求人情報を多数扱っております。
自動車業界に精通したキャリアアドバイザーが、応募書類の書き方や面接の心構えなど様々な面でのサポートをいたします。未経験可の求人も多数ありますので、他業種からの転職になる方もぜひお気軽にご相談ください。